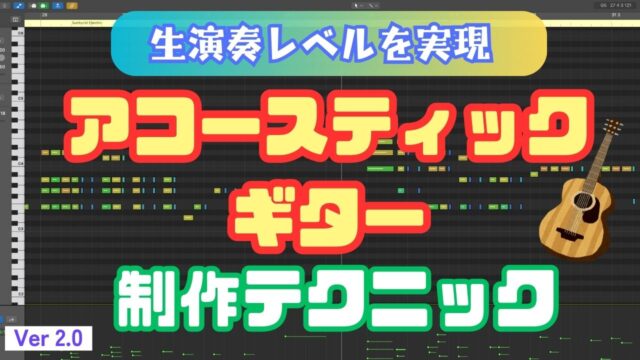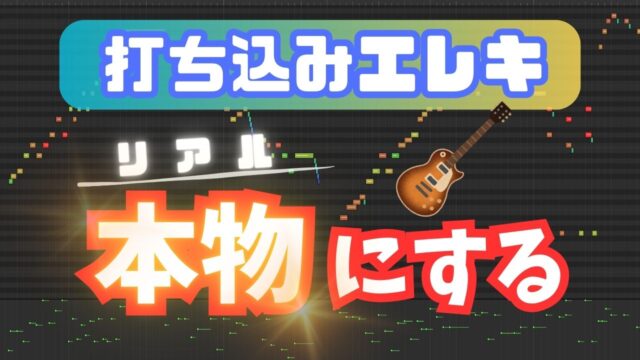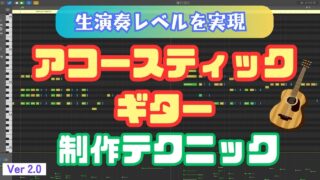ファンクやフュージョン、ロックなどのジャンルで多用されるベーステクニック、スラップ(チョッパーベース)。
派手でカッコいい演奏ですが、DTM打ち込みでリアルに表現するのは難易度が高いです。
この記事では「存在感のあるカッコいいスラップベースを打ち込みでリアルに再現」する方法を、テキストと動画を使ってわかりやすく解説します。
このぐらいのレベルの再現度を目指します!
具体的な打ち込み方法はもちろん、おすすめの音源や音楽ジャンル別の使いどころなども解説しています。
この記事で公開しているテクニックを最後まで読めば、ワンランク上の音楽制作技術を必ず身につけることができます。
生演奏のようにリアルなスラップベース打ち込み術、ぜひ習得しましょう!
解説動画
基本的にはこの動画を見れば完璧ですが、この記事ではテキストを動画を使って詳細を解説していきます。
【DTM機材ならサウンドハウス】
おすすめスラップベース音源3種
まずは音源の選択です。
スラップのような独特の奏法の再現はDAWデフォルト音色では難しいので、ここでは私のおすすめの3つの音源をご紹介します。
①Organic Slapped Bass
最初は私のイチオシ音源、Fujiya Instruments様の「Organic Slapped Bass」です。
パキパキとした硬いスラップ音は、ファンク・フュージョンはもちろん、ロックやポップスなど、ジャンルを問わず使用できます。
アーティキュレーションも豊富で、多彩な演奏表現ができます。
Fujiya Instrumentsの公式サイトは下記ボタンから飛べます。
②TRILIAN
ベース音源の定番であるSpectrasonics「TRILIAN」にもスラップ音色が用意されています。
独特の粘りのある音色で、80年代シティポップを彷彿とさせます。重低音の響きと厚みは、さすが定番といったところです。
ポップス系のスラップで存在感を出せると思います。
スラップに限らず、エレキベース・シンセベース音源として非常に重宝するので、購入しておいて損はありません。
③WAVES BASS Slapper
最後はWAVES BASS Slapperです。プラグインエフェクトで有名なWAVESですが、スラップ音源も出してます。
メカニカル・テクニカルな音色は、複雑なパート構成の現代ポップスと好相性です。
細かい調整が可能で多くのジャンルに対応できますが、設定によって音色がかなり変化するため、やや上級者向きと言えるかもしれません。
スラップベース音源は他にも多数ありますが、とりあえずこの3種類から選んでおけば間違いはありません。
ご自身の音楽ジャンルやスタイルに合わせて選択しましょう。
スラップベース入力の基本
ここからは具体的にスラップベースの打ち込み方法について解説していきます。
①オクターブ演奏
まずはスラップの基本の動きと言えるオクターブ演奏です。
高い方の音はデュレーションを短く、ベロシティは強めにします。
高い音をキレ良く短くするとスラップベースらしさが増します。
② 7度の音を加える
次は7度の音を加えて動きを出します。最高音よりもひとつ下の音を強くするのがポイントです。
③ミュートノイズ
デュレーションを極端に短くしたミュートノイズを配置します。これを入れることで
スラップ感が一気にアップします。
ノイズを入れることで、ライブ感を強めることができます。
④シンコペーション
シンコペーションを入れて躍動感を出しましょう。
シンコペーションとは、前の拍に食って入ることです。効果的に使えば楽曲全体のノリをよくすることが可能です。
積極的に入れてリズムを感じさせるフレーズを作りましょう。
⑤指弾きフレーズ
スラップしない指弾きのフレーズを混ぜて変化をつけます。
「静」と「動」を意識させて、聞き手に変化を感じさせましょう。
このフレーズでテンポを上げれば、かなりベースソロ感が出ます。
ここまでがスラップ打ち込みの基本です。ここからは、これらの基本を組み合わせてフレーズを作っていきましょう。
音と光の国内最大総合デパート DTM機材はサウンドハウス
フレーズの組み立て
ここからは実際にスラップベースのフレーズを作成していきましょう。
基本となる最初の2小節をリピートし、それを少しずつ変化させてスラップベースソロとして
フレーズを展開させていきます。
この方法なら、最初のフレーズさえ決めてしまえば、あとは少しの変化でフレーズを発展させることができます。
①基本フレーズ 1回目
まずは基本となるフレーズを作ってみましょう。ノートを少し重ねてハンマリング、部分的にスライドも入れてみます。
多くのベース専用ソフトでは、キースイッチなどでハンマリングやプリング、スライドを表現できます。
②3連符とシンコペーション
リピート2回目は、先ほどのフレーズに3連符とシンコペーションを入れます。
かなり変化を感じられると思います。
③和音とステレオ感
3回目は高音域に和音を入れ、ステレオ感を出すためにパートを増やし、それぞれを左右に振ります。
④フィルイン的スライド
最後は力強い演奏と長めのスライドで次につなぎます.
⑤実際のテンポで再生!
ここまで来れば完成です!実際のテンポで再生してみましょう。
難しそうに見えるかもしれませんが、実際には基本のフレーズを組み合わせているだけです。
練習次第では、生演奏にかなり近い表現も可能です。ぜひチャレンジしてみましょう!
【DTM機材ならサウンドハウス】
ジャンル別の使いどころ
ここまではスラップソロの打ち込みを解説してきましたが、やはりベースは他のパートと合わせてナンボです。
ここからはいろいろな音楽ジャンルにおける、曲中でのスラップベースの使いどころをご紹介します。
①スムースジャズ・フュージョン
まずはミドルテンポのスムースジャズ・フュージョンです。
スラップといえば早いテンポのファンク・ロック系をイメージしやすいですが、スローテンポやミドルテンポのスモーキーな曲にもよく似合います。
この系の曲にスラップを入れる場合は
「あまり派手に動かさず控えめにスラップを鳴らすようにし、それでいて存在感を主張できる」
そんなイメージを目指しましょう。
②シティポップ
80年代シティポップや、2000年台のネオ・シティポップでもスラップベースが多用されています。
この場合はカッティングギターやブラスセクションと合わせ、ファンクに寄せてみるのもおすすめです。
③ゲームなどのBGM系
スラップベース特有のレトロな雰囲気を生かし、ゲームや動画のBGMとしても使えます。
シューティングやアクション系で、派手な雰囲気を出しましょう。この場合はベースソロばりに動きを出すのもアリです。
④テクニカルなファンク
ファンク系のテクニカルなカッティングギターにも、スラップベースはよく似合います。
リズミカルでメカニカルなイメージを最大限に引き出せます。
まとめ
スラップベース打ち込みは難易度が高いですが、うまく再現できれば最高にかっこいい仕上がりになります。
ここまでのテクニックを駆使し、ぜひスラップベースを取り入れた楽曲制作にチャレンジしましょう!
このブログでは、DTMで生演奏のようなクオリティーを出すためのテクニックを他にも多数公開しています。
ぜひ参考にして、より高いレベルの楽曲制作を目指しましょう!
【DTM機材ならサウンドハウス】